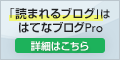おはようございます、なべやすです。
私は、子どもの頃からの恐竜愛好家です。
そんな私が子どもの頃から変わらず好きな恐竜は、首長竜の「プレシオサウルス」です。
恐竜好きだとティラノサウルスやトリケラトプスなどのメジャーな恐竜が好きなのかと思われますが、なんと言ってもプレシオサウルスが私の中でのナンバーワン恐竜です。
プレシオサウルスは、かつて世界的に有名になった未確認動物UMA、ネス湖のネッシーの正体ではないかと世間を賑わせたこともあります。
しかし、最近になってその正体は、プレシオサウルスどころかネッシーの存在自体までもが否定されるようになってしまいました。
これは、恐竜好き!UMA好き!の私にとって一大事です。
当記事ではネス湖のネッシーとプレシオサウルスについて、恐竜愛好家の視点から詳しく解説していきます。
また、ネッシーが首長竜プレシオサウルスの生き残りであるという仮説の矛盾や不合理を、独自の視点から解説します。
- 世界中で最も有名なUMA|ネス湖のネッシー
- ネッシー=プレシオサウルスの生き残り説になった理由は?
- 未確認動物UMA|ネッシーはプレシオサウルスの生き残りなのか?
- ネッシーの正体がプレシオサウルスではないと考えられる理由
- プレシオサウルスの生き残りではないとすればネッシーの正体は何なのか
- 近年の研究報告ではネッシーの存在そのものが否定された
- 【衝撃事実】プレシオサウルスは恐竜ではない!
- これからも化石の調査や研究により恐竜の定説は変わって行く
- 最後に
世界中で最も有名なUMA|ネス湖のネッシー
プレシオサウルスに興味を持つようになったきっかけは、かの有名なネス湖のネッシーの影響です。
ネッシーについては既にご存知の人も多いかもしれませんが、簡単におさらいをしておきます。
ネッシーとは

ネッシーは、スコットランドのネス湖に住むとされる伝説の生き物です。
目撃者の証言では首が長くて胴体がずんぐりした姿で描かれることが多く、恐竜時代にいた首長竜プレシオサウルスに似ていると言われています。
ネッシーの存在を裏付ける証拠はありませんが、現在でも世界中の人々が湖に訪れて目撃情報を寄せています。
上記のように、ネッシーは言わずと知れた未確認動物界のスーパースターです。
もはや、世界中でネス湖のネッシーを知らない人はいないと言えるほど有名な伝説のUMA(未確認動物)と言えるでしょう。
UMAという呼称は、英語で「謎の未確認動物」を意味する Unidentified Mysterious Animal (和製英語)の頭文字をとったものである。 實吉達郎に依頼された1976年当時の『SFマガジン』編集長の森優(後の超常現象研究家の南山宏)が、UFO(Unidentified Flying Object)を参考に考案したものであり、初出は、實吉達郎の『UMA―謎の未確認動物』(1976年、スポーツニッポン新聞社出版局)であるという。
ネッシー最初の目撃は今から1400年以上前

スコットランドのネス湖のネッシー伝説は、今からさかのぼること1400年以上前の西暦565年に記された「聖コロンバ伝」に見られる、水棲獣との遭遇が最初と言われております。
ネス湖は、イギリス・スコットランド北部ハイランド地方にあるイギリス最大の湖で、長さが約35キロメートル、幅約2キロメートルの非常に細長い湖で水深は最大で約230メートルもあります。
1933年以降には、そのネス湖でネッシーの目撃が多くみられるようになり、写真や映像による目撃報告によって世界中にネス湖の怪獣伝説は広まりました。
そしてネッシーは、スコットランドにあるネス湖に棲息するUMA(未確認動物)として、1970年代に一大ブームを巻き起こしました。
ネッシー(英: Nessie)は、イギリス、スコットランドのネス湖で目撃されたとされる、未確認動物「ネス湖の怪獣 (the Loch Ness Monster、ロッホ・ネス・モンスター)の通称。未確認動物の代表例として世界的に知られ、20世紀最大級のミステリーとして語られてきた。
引用元:ネッシー - Wikipedia
「外科医の写真」がネッシーの存在を確信する一枚となった
ネッシーの正体はいったい何なのだろう?と誰もが思う中、ネッシーの正体こそ私の好きなプレシオサウルスの生き残りではないか?という説が、1970年代後半の日本でも度々話題になっておりました。
それは当時、子どもであった私にとって、とても夢のある話であり、ネッシー=プレシオサウルスに大きく興味を抱くようになります。
そして、ネッシーがプレシオサウルスの生き残りであると信じるようになったのは、ある一枚の写真を見たことがきっかけでした。
それは、長らくネッシーの代表的な写真として世に知られることになった、通称「外科医の写真」です。

後にトリック写真(ねつ造)と判明されたネッシーの写真「外科医の写真」も、子どもの頃の私にとってはかなり衝撃的な写真で、ネッシーの存在を確信する一枚となりました。
ネッシー=プレシオサウルスの生き残り説になった理由は?
ネッシーがプレシオサウルスの生き残りであるという仮説のほとんどは、目撃されたネッシーの写真からにあります。
通称「外科医の写真」以外にも、目撃写真はネッシーが湖上に首を伸ばした姿を捉えているものばかりです。
これらの写真を見た多くの人々は、ネッシーがプレシオサウルスに似ていると感じたことに違いないでしょう。
様々な目撃写真と共に、氷河期に形成された深くて寒い湖のどこかで、プレシオサウルスが絶滅せずに隔離されて生き延びた可能性があると考えられるようになったのかもしれません。
未確認動物UMA|ネッシーはプレシオサウルスの生き残りなのか?

首長竜プレシオサウルスとは
プレシオサウルスは、中生代三畳紀からジュラ紀にかけて生息した海棲爬虫類の一群です。
首が長く、頭部が小さく、四肢がひれ状になっているのが特徴で、魚やイカなどを捕食していたと考えられております。
プレシオサウルスは肺呼吸をするので、水面に上がって空気を吸う必要がありました。
分類上は恐竜ではなく、現在のトカゲやヘビと近縁な分類群に属すると言われておりますが、卵を産むのではなく、胎生で子供を産んでいたと考えられています。
プレシオサウルス(トカゲに近いもの)
- 科名:プレシオサウルス類
- 全長:3.5m
- 食性:肉食(主にイカや魚)
- 生きていた時代:ジュラ紀前期
- 化石が見つかった場所:イギリス
参考:小学館の図鑑NEO[新盤]恐竜
プレシオサウルス(Plesiosaurus)は中生代三畳紀後期 - ジュラ紀前期に棲息していた首長竜の属の一つである。首長竜目 - プレシオサウルス科に属する。
ネッシーの正体がプレシオサウルスではないと考えられる理由

ネッシーの有名な目撃写真がニセモノと判明したり、他にも近年の研究結果ではネッシーの存在自体が否定されてきております。
少なくともネッシーの正体がプレシオサウルスなどの恐竜ではないことは、間違いなさそうです。
ネッシー伝説は、いったいどうなってしまうのでしょうか?
ここからは、ネッシーがプレシオサウルスでないと考えられる驚くべき理由について、独自の視点から解説します。
ネッシーとプレシオサウルスでは大きさが違いすぎる
ネッシー=プレシオサウルス説ですが、以前からネッシーの正体がプレシオサウルスの生き残り説を覆すとも言える理由が私の中ではあります。
まず一つは、ネッシーの大きさです。
ネッシーの目撃例は、10メートルを超える大型のものも多くあります。
しかし、現在の恐竜図鑑に載っているプレシオサウルスの大きさと比較すると、その大きさはだいぶ異なっているのです。
私が子どもの頃に想像していたプレシオサウルスの大きさとはかなり異なっていて、現在の定説では恐竜図鑑を見ても大きさは約3.5メートル、ウィキペディアでも2~5メートルと書かれております。
どうやら想像していたよりも、プレシオサウルスはかなり小さかったようです。
少なくとも、プレシオサウルスがどんなに成長しても10メートルに達することはなかったでしょう。
私が子どもの頃に想像していたプレシオサウルスは、長い首を水面から出し、大きな体で悠然と海を泳いでいたものだと想像しておりました。
しかし、最近の説では、その大きさからして、どちらかと言えば機敏な動きで泳いでいたのではないかという説も出ていおります。
プレシオサウルスは首をもたげない?
ネッシーの目撃写真でよく見られるのが、首長竜のような生物が首をもたげている姿です。
しかし、そのような目撃写真が逆にネッシーの存在を否定することになります。
以前、テレビ番組で恐竜くん(田中真士さん)が、プレシオサウルスは首の構造から首を下に動かすことはできたけど、ネッシーの目撃写真のように首をもたげることはできなかったと説明しておりました。
いろいろ調べてみると、プレシオサウルスは長い首と小さな頭を持ち、水中で素早く動くことができたが、首をもたげることはできなかったという説が確かにあります。
プレシオサウルスは首をもたげないという説が本当だとすると、目撃写真として撮られた多くのネッシーは少なくともプレシオサウルスではなことになります。
プレシオサウルスの生き残りではないとすればネッシーの正体は何なのか

ネッシーの正体がプレシオサウルスの生き残りではない可能性を説明しましたが、だとするとネッシーの正体は何なのでしょう。
ネッシーの正体については様々な説がありますが、私が考えるネッシーの正体をいくつか紹介していきます。
目撃者の誤認
ネッシーは数多くの目撃情報や写真、映像が報告されています。
しかし、これらの証拠すべてが本物と考えるのは、決して妥当ではありません。
写真や映像が不鮮明だったり、目撃情報がネス湖に現存する他の生き物や湖面の波、流木などの誤認であったりする可能性も十分考えられます。
実際に、ネス湖では様々な科学的調査が行われてきましたが、ネッシーの存在を確かめることは今まで一度もできていません。
したがって、ネッシーの正体は目撃者の誤認というのは、有力な説の一つとして考えることができます。
ネッシー伝説そのものがフェイク
未確認動物UMAの中でも知名度と人気のあるネッシーには、たくさんの目撃写真や映像が報告されています。
その反面、それら写真や動画の多くがニセモノだったという事実もあります。
かの有名な「外科医の写真」でさえ、フェイク写真でした。
少し大胆な考えではありますが、ネッシー伝説そのものがフェイクであったなんてこともあるかもしれません。
現存する生き物
ネッシーがいるとされているネス湖は、水深も深く未知の巨大生物が存在しても決して不思議ではありません。
しかし、ネッシーの正体を現存する生き物と考える方が現実的です。
最も有力で有名な説は、大型化したウナギと言われております。
仮にウナギでなかったとしても、ネス湖に生息する生き物をネッシーと誤認したと考える方が素直ではないでしょうか?
他にも、ネス湖ではまだ発見されてない、既知の生き物を目撃した可能性も十分考えられます。
近年の研究報告ではネッシーの存在そのものが否定された
多数の目撃例により、長きに渡って物議を醸しだしてきたネッシーも、ついにその存在を否定する研究報告が発表されました。
2019年9月5日にニュージーランドのオタゴ大学の研究者が、ネス湖のネッシーについて以下の報告をしております。
ニュージーランドのオタゴ大学の研究者が9月初め、未確認生物ネッシーの正体は大ウナギである可能性があると発表した。eDNAと呼ぶ最新のゲノム解析技術を使って調査した結果、ジュラ紀の爬虫(はちゅう)類を示す証拠は見つからず、サメやナマズである可能性も見当たらなかったという。※日経ビジネスホームページ2019年9月20日から一部引用
この研究報告によって、ネッシーの正体はプレシオサウルスどころか、その存在すら科学的に否定されることになってしまいました。
ただし、ウナギのDNAが多く検出されているとの報告もあったので、ネッシーの正体はもしかしたら今まで見たこともないような巨大ウナギなのかもしれません。
いずれにしても、私にとっては夢がなくなるような話で、何とも寂しい研究報告と感じてしまいます。
【衝撃事実】プレシオサウルスは恐竜ではない!
そんなネッシーの正体として考えられてきたプレシオサウルスですが、恐竜図鑑などにも載っているとおり、世間一般では恐竜として知られております。
ところが、分類上では恐竜ではなく水棲爬虫類に分類されているのです。(恐竜の定義は直立歩行をする爬虫類と言われております。)
学術的には「陸棲の直立歩行をする爬虫類」のみを恐竜と定義するため、本種を含めた海棲の首長竜や魚竜は分類上は恐竜ではない。プレシオサウルスは首長竜では最初期の種である。一時は首長竜が全てプレシオサウルス属に分類されたこともあり、種の数が90を越えたこともある。しかし研究が進むにつれ分類が整理され、現在はプレシオサウルス・ドリコデイルスなど数種がプレシオサウルス属に分類されている。
(引用元:ウィキペディア)
つまり、プレシオサウルスどころか、翼竜プテラノドンも分類上では恐竜でないことになります。
また、不思議なことにプレシオサウルスは爬虫類でありながら卵ではなく赤ちゃんを産んだという説もあるようです。
現在、生息する哺乳類の「カモノハシ」が哺乳類でありながら卵を産むことと、プレシオサウルスは逆の感じです。
「プレシオサウルス」も「カモノハシ」のどちらも、なんとも不思議な生き物です。
これからも化石の調査や研究により恐竜の定説は変わって行く
化石の発掘調査や研究により定説が変わって行く恐竜。
あのティラノサウルスも私が子どもの頃はゴジラのように直立の2足歩行で歩き、爬虫類のような鱗状の皮膚で想像図が描かれておりました。
しかし、現在では大きな頭と太い尻尾を水平にし、前傾姿勢で2足歩行するのが定説となっております。
皮膚に関しても羽毛で一部が覆われていたのではないかという説も出てきたりしており、私が子どもの頃に目にしていたティラノサウルスとは随分と変わってしまいました。
私が子どもの頃に本などで見てきたティラノサウルスを始めとした恐竜の想像図は随分と変わってきており、これからも調査や研究などによって恐竜の定説は更に変わって行くものかと思われます。
スピノサウルスの定説が覆された!
最後に

この記事にも書いてきたように、ネッシーの正体については科学的な証拠が不足しており、未だに確定的な結論を出すことは難しいのが現状です。
ただし、ネッシー=プレシオサウルスでなかったとしても、ネス湖で新たな巨大生物の発見がある可能性は否定できません。
ネッシー伝説は人々の想像力やロマンを刺激するものであり、その魅力はこれからも失われることはないでしょう。
最近では、2023年8月26日と27日の2日間にわたってネッシーの捜索が行われました。
この調査は半世紀で最大規模とされ、200人ほどのボランティアも国内外から駆けつけたとのことです。
これからも、ネッシー調査や研究が続いていき、新たな情報や発見が出てくることを期待しています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。